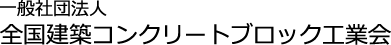ブロック塀大事典
6-2. 用語解説
- コンクリートブロック
-
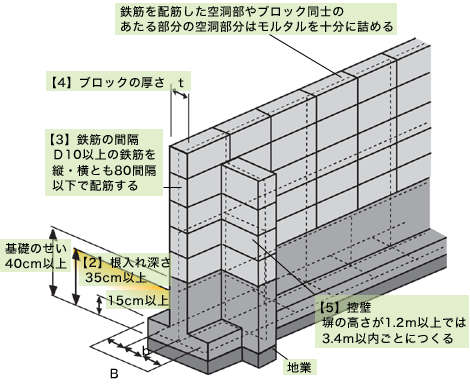
配筋のための空洞をもつコンクリートブロックのことで、その種類・品質はJIS A 5406で規定されています。ブロック塀に使われるコンクリートブロックの種類は、一般にB種かC種と呼ばれるものを使います。
また、写真のような形の種類があり、奥が塀の水平端部に使われる隅用ブロック、中央が横筋を入れられるよう溝を付けられた横筋用ブロック、手前が一般の部位の使われる基本ブロックです。
この他にも塀の頂部に使われる笠木ブロック、門柱に使われるブロックなどがあります。また、表面に化粧を施した化粧ブロックがあります。この化粧ブロックは一般にJISに沿ってつくられた同等品として使われています。
- 地盤
- 塀をたてる地面のことで、塀が沈んだり傾いたりしないような地盤の固さが必要です。また、基礎から一体となったブロック塀が地震などで転倒しないように横から支えるのもこの地盤です。
- 地業
- 地盤上に直接砕石などを敷いて、モルタルで用いて基礎の下を固める作業です。
- 基礎
-
基礎は耐久性のある鉄筋コンクリートでつくります。この基礎は塀と一体となって地震でも倒れないように、土の中に35cm以上埋めなければなりません。この埋め込む深さを根入れ深さといい、法律で決まられています。
基礎は地盤の固さ(強さ)により長方体(I形)やL形や逆T形とします。ブロック塀の施工で一番悪い工事とは、基礎がなく、モルタルを打ち込んでこの上に直接ブロックを積み上げる工事をすることです。
- 鉄筋
-
鉄筋には塀を倒そうとする横からの力に抵抗する縦筋と、塀の長さ方向を一体とする役目をもつ横筋があります。いずれも、節のある鉄筋(異形鉄筋)で径10mm(呼称:D10)のものを縦方向でブロック2列(塀の高さにより1列)ごと、横方向では3段ごとに入れます。
なお、縦筋は基礎から立ち上げ、塀の高さ分を1本として末端をU形かL形に曲げておきます。鉄筋を途中で継ぐと地震のときに鉄筋が塀から抜けて、倒れることがあり非常に危険です。
- 笠木
- 塀の一番上におく五角形状のブロックで、塀の中に雨水が入ることを防ぎ、塀を長持ちさせます。笠木はモルタル等で塀に固定して浮きや落下がしないよう注意します。
- 控え壁
- 控え壁は地震などの横からの力に抵抗するためにつくられる壁です。控壁は高さ1.2mを越えるの塀に必要で、長さ方向に3.4m以内ごとにつくります。控え壁は、塀と一体とするために基礎や配筋も同じようにつくります。
- 透かしブロック
- 塀のデザインや、風通しにためにつくられたブロックです。多くの透かしブロックは、長方形で鉄筋が入る溝がありません。したがって、これを連続して並べたり多用すると大事な鉄筋の量が不足したり、入れられなくなったりするので使い方には注意が必要です。
透かしブロックを使うときは、配筋用の溝があるものを使ってください。 - 充填モルタル
- このモルタルは、ブロックの空洞部に入れられた鉄筋の周りに詰められるものと、隣り合うブロック部分にできる空洞部(たて目地)の部分に詰められるものがあり、いずれもブロック塀を一体とするため、また鉄筋のさびなどを防ぐ重要な役目をします。
- 目地モルタル
- このモルタルはブロックを積むときに使うもので、ブロック同士をくっつける役目をします。積み上がったブロックが1枚の壁としての強さや塀として長くもたせるためには、隙間がなくブロック周囲全体にモルタルが行き渡ることが重要です。
- モルタルの調合
- モルタルはセメント1に対して砂2.5(容積比)として、必要に応じてモルタルの品質をあげる添加剤を入れます。
- 目地
-
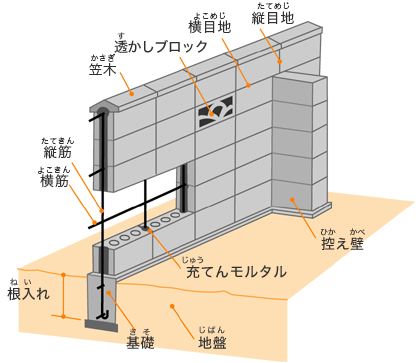
ブロックの積み方で芋目地と破れ目地とに分かれます。
芋目地は目地の線が縦横に通った目地(下の参考図)になります。芋目地は目地の部分に補強鉄筋を通して補強するとともに、積みやすく、また破れ目地よりも芋目地の方がかっこよい(美しい)というイメージがあるようです。
破れ目地は横方向の目地が通り、縦方向は横目地によって切れる目地になります。破れ目地は、煉瓦のような組積造の場合に採用する場合が多く、上からの重さを分散し、壁の強さや粘りなどが増す利点があります。
ただし、80cm間隔に入れるたて筋に、1段ごとに積むブロックの中央の穴のなかを通さなければならない難しい作業が増えることになります。
- 白華(エフロレッセンス)
- 主に水に解けたセメントのアルカリ成分が、空気中の炭素ガスなどと結び合ってコンクリート(ブロック)表面に白く現れる現象です。この現象はコンクリート製品の宿命ともいわれていて、製品の見栄えを悪くしますのでしばしば問題視されますが、製品の性能が悪くなることはありません。
- 中性化(炭酸化)
- ブロック、目地モルタル、充填モルタルはセメント成分の強いアルカリ性(ペーハー12.0~13.5)があります。しかし長い時間をかけて空気中にさらされ、空気中の炭酸ガスや酸性雨などによってアルカリ成分が分解されて、ペーハーが低下し8.5~10.0程度になる現象をいいます。この中性化が進むと塀の内部に配筋されている鉄筋がさびやすくなり、さびが進めば塀の構造上危険な状態になります。
- 凍害
-
凍害には2つのケースがあります。いずれも気温差の大きい裏日本、北海道などの寒冷地で問題視されることがあります。
一つは、コンクリートの固まり始めるころに、コンクリートの中の水が凍ったり、解けたりの繰り返しでコンクリートの強さが弱くなったり、コンクリートの表面の部分から壊れはじめたりする現象で「初期凍害」といわれ、もう一つは固まったあとのコンクリートの中で、少量の含まれた水が凍ったり、溶けたりを何百回も何千回も繰り返して、コンクリートの状態を徐々に悪くする現象で、これを「凍害」と区別しています。